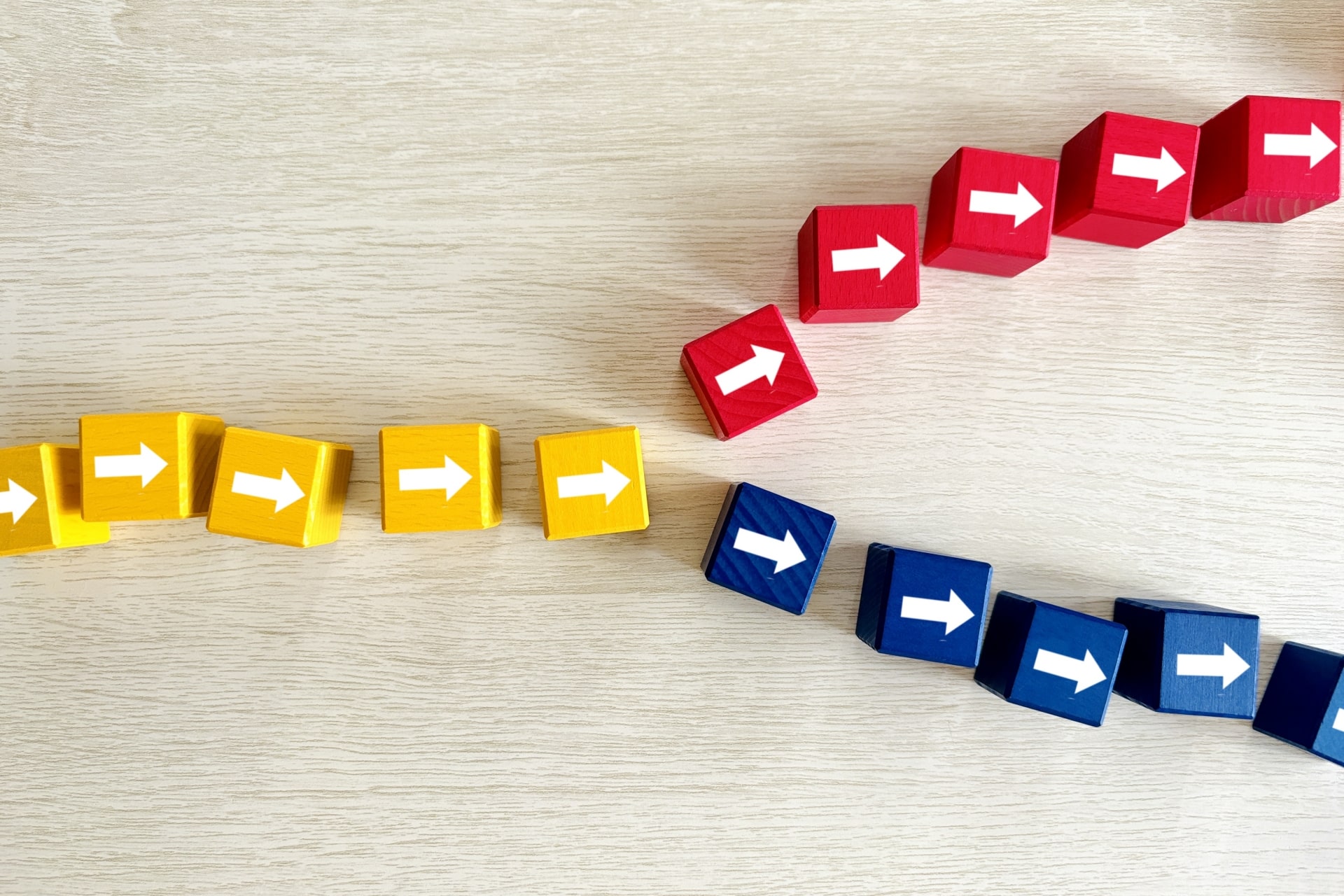受験に無事合格した後、多くの保護者の方にとって気になるのは、「塾へのお礼」ではないでしょうか?
これまでお世話になった塾や講師に対して、どのように感謝の気持ちを伝え、お礼をすればいいのか、悩まれる保護者の方は少なくありません。
「お礼の品物は必須なの?」
「何を贈るとよいの?」
「いくらくらいの品物が適切?」
「お礼の品としてNGなのは?」
「塾がもらって困らないのは、どんなもの?」
こうした疑問は、お礼が遅くならないよう、早めに解消しておきたいところですよね。
そこで今回は、合格後、塾へお礼の品が必要かどうか、贈り物をするとしたら、どんなものがおすすめか、塾への贈り物を選ぶ際に、注意しておきたいことは何か、「のし」やお礼状についてどうするといいのかについて、ご紹介します。
合格したときや塾を辞める時にお礼に何か渡すべき?

実は、志望校に合格した際や塾を辞める際に、お礼の品は必ずしも必要ではありません。
何かを渡してもよいですし、反対に何も渡さなかったとしても、失礼に思われたりマナー違反となることはありません。「渡しても渡さなくても、どちらでもいい」ものです。
ただ、感謝の気持ちを形のあるものと一緒に伝えたいという方も、いらっしゃると思います。
そうしたとき、できれば喜ばれるものを贈りたいですよね。
ここからは、どんなものがお礼の品におすすめかについて、ご紹介していきます。
お礼の品を渡すなら何がおすすめ?

もしお礼の品を渡すとしたらどういったものがおすすめか、例を挙げながらご紹介します。
菓子折りやコーヒー、紅茶など
菓子折りは塾への贈り物としても非常にポピュラーで、かつ喜ばれます。
特に、個包装された焼き菓子などは日持ちし、シェアもしやすいため、そうした面からも優れた贈り物です。
また、コーヒーや紅茶なども喜ばれます。休憩中や授業の間など、ちょっとした時間にも飲みやすく、事務仕事のお供にもなります。講師にとっても、助かる贈り物でしょう。
賞味期限をあまり気にしなくてもよいため、負担になりづらいのもポイントです。
クオカードや商品券、金券
クオカードや商品券、金券は塾への贈り物としてポピュラーです。
場所も取らず保管も簡単で、使い方にも幅があるため、受け取る側に負担が少ないのが特徴です。
「もらって困る」ことが少なく、贈る側としても、安心して渡すことができます。
そのほかにも、スタバを使用しやすい地域であれば、スタバカードなども喜ばれるでしょう。
ただし、こうした贈り物の受け取りを禁止している塾もあるため、その点は確認が必要です。
ギフト用のボールペンや万年筆など
講師個人への贈り物としては、ギフト用のボールペンや万年筆といった、文房具もおすすめです。
文房具は、塾講師にとっての必需品。ギフト用の文房具は、その高級感からさまざまなシーンで活躍します。
例えば、三者面談を思い浮かべてみてください。
しっかりとした万年筆を使う講師は、それだけで印象が変わりますよね。こうしたシーンで使いやすい文房具は、講師にも喜ばれやすいといえます。
もし、個人塾や、講師個人への贈り物を探している場合は、検討してみてはいかがでしょうか。
カタログギフトもおすすめ
特定の品物ではなく、カタログギフトを選択するのもオススメ。
特に、「何を贈ったら喜ばれるのかわからない」という場合に、選びやすい贈り物です。
たくさんの商品の中から講師が好きなものを選べるため、品物選びの失敗を防ぐことができます。
講師の好みを知らなくとも喜ばれるギフトを贈れるという点で、とても良い選択肢といえるでしょう。
お礼の品を選ぶ際の注意点

お礼の品を選ぶ際には、いくつか注意点があります。それを、確認しておきましょう。
渡せるかどうか確認しておく
お礼の品を渡してもよいかどうか、どんな品物なら渡してもよいか、事前に確認しておきましょう。
菓子折りまで禁止しているところは少ないですが、塾によっては、特定の種類の品物は受け取らないようにしている場合もあるからです。
そして、そのルールは塾によって異なります。
「クオカードや商品券、金券の類は受け取らない」という塾や、金品の受け取りを一切禁止している塾、講師個人に宛てたお礼の品を受け取ることを禁止している塾もあります。
教室長などの責任者に、「お礼の品物を贈りたいのですが、ルールなどはありますか?」と、事前に確認を取ってから購入すると、間違いがないでしょう。
現金やお酒は避ける
お礼として現金やお酒を贈るのは、避けるようにしましょう。
現金やお酒は塾によって禁止されている場合があり、かえって迷惑をかける可能性があります。集団指導塾の場合、特にその傾向は強くなります。
これらをお礼の品物として選ぶのは、避けたほうが無難でしょう。
塾へのお礼にのしやお礼状は必要?

お礼の品物を贈る場合、「のし」やお礼状についてどうすればいいかも、迷うところかと思います。この点についても、ご紹介します。
のしはあってもなくても良い
塾へのお礼の品に、必ずしも「のし」をつける必要はありません。
もし、「つけていないと、失礼になってしまいそうで……」と感じるのでしたら、以下の点に気を付ける程度で十分です。
- 表書きは「お礼」もしくは「御礼」
- 水引は「紅白」の「蝶結び」
- 名入れは「名字のみ」もしくは「塾生のフルネーム」
- 毛筆もしくは、筆ペンを使用する
のしをつける場合は、こうした点を覚えておくと、気持ちがより伝わりやすいでしょう。
お礼状や添え状を添えると丁寧
塾にお礼の品物を渡す際は、お礼状や添え状を添えると、より丁寧に感謝の気持ちを伝えられます。
ただし、お礼状や添え状は必須ではなく、ないからといって失礼にあたるわけではありません。この点は、安心してください。
もしお礼状や添え状を書く場合、その文章は難しいものでなくても大丈夫です。
感謝の気持ちを簡潔に伝える一文を手書きでするだけでも、気持ちは十分伝わります。
お手紙があると喜ばれる
もし感謝の気持ちを伝えるのであれば、お手紙は大変喜ばれます。
いただくと非常にうれしいもので、保護者の方からのお手紙であっても、塾生からであっても、大きな元気をもらえます。もらった手紙を宝物としてずっと持っているという講師も多いです。
書く際の作法についてですが、こちらは過度に気を遣う必要はありません。
手紙は気持ちですので、作法に則った文章を無理に考える必要性は薄いといえます。
それがお子さんからのお手紙であればなおのこと。格式ばった文章よりも、ストレートに気持ちをつづった手紙が、より喜ばれるでしょう。
もし保護者の方が手紙を書く際、作法を気にされるようでしたら、
- 季節のあいさつ
- 合格したことの報告
- 感謝、お礼の気持ち
- 結びのあいさつ
という流れを意識してみてください。これで十分、作法に則ったお手紙であると感じてもらえます。
また、手紙は活字で印刷したものでなく、手書きであると、気持ちがより伝わりやすくなるでしょう。
お礼の品の金額相場はいくら?

お礼の品の価格の目安は、3,000〜5,000円ほどが一般的です。
贈り物としてチープな印象にならず、塾としても受け取りやすいでしょう。もちろん、5,000円を超えても問題ではありません。
ただ、10,000円を超えると、受け取りづらいという気持ちが先立ってしまったり、かえって気を遣わせてしまう可能性があります。
贈り物をする際に大切なのは、あくまで気持ちです。金額にとらわれすぎず、感謝の気持ちを伝えることを大切にしてみてください。
お礼の品を渡すタイミング

最後に、お礼の品を渡すタイミングについても、ご紹介します。
受験が終了した時
お礼の品物を渡すタイミングの一つとして、受験が終了したときが挙げられます。それも、他校の合格発表が済んでからが、よいタイミングでしょう。
合格発表は、受験する学校や塾生ごとにまちまちです。自分の受験が終わっても、ほかの塾生はまだ受験の最中である場合があります。
そうした塾生を指導するため、すべての受験が終了するまでは、塾としても、緊張感を持って臨んでいます。この点を配慮すると、塾や周りの塾生も助かるしょう。
もし、合格発表から受験シーズン終了までの間が空く場合、先に電話でお礼を伝えておくことがおすすめです。
その後、他校の合格発表が終わってから訪問すると、より丁寧にお礼の気持ちを伝えられるでしょう。
塾を辞める時
お礼の品物を渡すもう一つのタイミングとして、塾を辞める時が挙げられます。つまり、最後の授業の日です。
送迎の際に、手短に渡すとよいでしょう。お子さんに品物を持たせる形で渡しても、問題はありません。もちろん、日を改めて訪問することも可能です。
保護者の方が訪問してお礼の品物を渡しても問題ありませんが、お子さんと一緒だと一層喜ばれるでしょう。
まとめ
合格したあと、塾へのお礼の品物を贈りたい場合、菓子折り、コーヒーや紅茶などがポピュラーです。また、クオカードや商品券なども喜ばれやすい品物といえます。
講師個人に宛てた場合は、ギフト用のボールペンや万年筆といった文房具も、喜ばれるでしょう。もし講師の好みがわからない場合、カタログギフトであれば、品物選びの失敗を防ぐことができます。
反対に、現金やお酒は、避けたほうが無難です。品物を選ぶ際は、塾がルールを設けていないか事前に確認しておくと、間違いがありません。
また、あまり高すぎる品物は、かえって気を遣わせてしまうこともあります。この点は、気を付けておけるとよいですね。
お礼の品物を渡すときは、他の受験生が受験を終えたタイミングだと、渡しやすいでしょう。合格発表から間が空く場合は、先に電話でお礼を伝えてから、改めて訪問すると、より丁寧な印象を与えられます。
今回は、「もし、お礼の品物を贈るなら、何がおすすめか?」というお話をさせてもらいました。
ご紹介した内容に加えて、真に塾や講師の励みになるのは、品物そのものではなく、皆様からいただくお礼の言葉であることも、覚えておいていただけると嬉しいです。