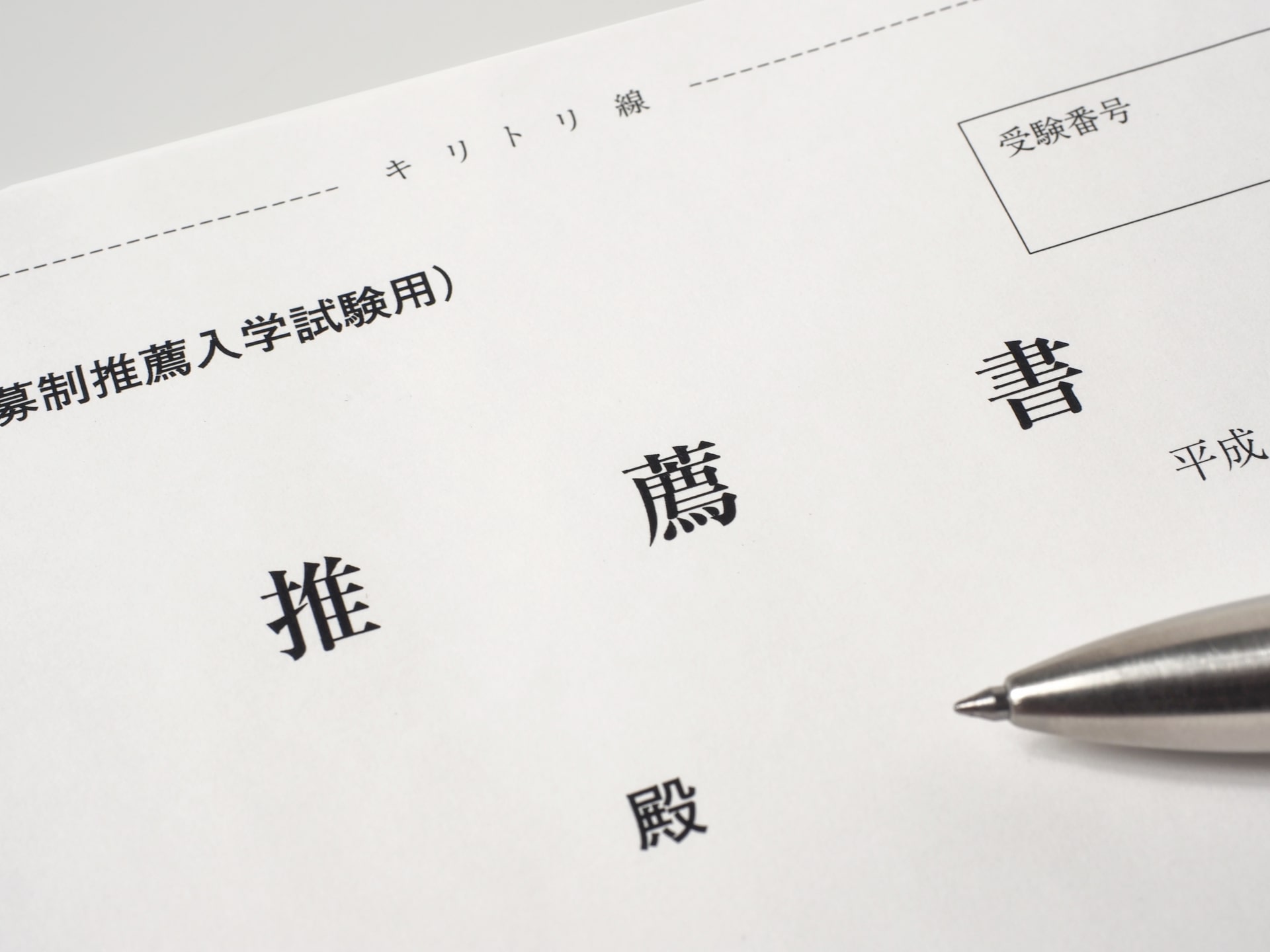
中学生の皆さんにとって、推薦入試という制度の名前は、頻繁に耳にするかと思います。そしてそれは、受験が近づいていくにつれて、日に日に増えていくことでしょう。
推薦入試は、内申点や面接、小論文などをもとに合否が決まります。また、多くの場合において学力検査がなく、かつ早い時期に進路が決まるメリットがあり、人気のある受験方法の一つです。
そこで今回は、推薦入試に興味がある中学生の皆さんに向けて、推薦入試とはどんな制度なのか、実施される試験内容、合否の決定方法、受けるためには何をするべきなのか、という点について、ご紹介します。
高校の推薦入試とはどんな制度?

まずは、高校受験における推薦入試がどのような制度なのかについて、知っていきましょう。
推薦入試とは?
高校受験における推薦入試とは、中学校のときの成績(内申点)や活動実績、面接や小論文などによる総合評価で合格者を決める入試形式です。
学科試験がない場合が多く、「一般入試とは違った観点から、受験生を選抜しよう」という意図が読み取れる形式だといえます。
そのメリットとしてはやはり、推薦入試に合格すれば、一般入試を受けずとも志望校に入学できる点でしょう。
ただし、誰でも受験できるわけではなく、一定の条件を満たした生徒のみ受験を許可されます。具体的には、中学校からの推薦と、それぞれの高校が設定した推薦基準に合致していること。この条件を満たすには、早期からの対策が必要となります。
また、高校や自治体によって、推薦入試を行っているかどうかが異なります。
つまり、「一般入試のみ」の高校があるのです。受験要綱の見直しがされる場合もあるので、自分が受験する年はどうか、しっかりチェックしておきましょう。
私立高校の場合、推薦入試の有無はそれぞれの高校の指針によって決定します。この場合も受験要綱の見直しがあれば変更されるため、同じようにチェックしておくことが大切です。
一般推薦入試
面接や集団討論、作文や小論文による試験に内申点をプラスして、さまざまな観点から受験生を見る入試形式が、一般推薦入試です。
基本的に、英語・数学・国語・理科・社会といった、「学力のテスト」はありません。
試験で見るのは、勉強の成果ではなく、それによって育んだ「思考力」に着目した選考であるといえます。
特別推薦入試
特定の科目や部活動、スポーツ、その他の活動で優秀な成績を収めた生徒を評価する入試形式が、特別推薦入試です。
「スポーツ推薦」、「一芸推薦」などもここに含まれ、「特色化選抜」や、「前期選抜」といった別名で呼ばれることもあります。
特別推薦入試は以下のような特徴を持ちます。
- 中学校側からの推薦は、基本転記に不要(必要な都道府県もあり)
- 受験には自己推薦が必要
- 高校によっては、学力検査が実施される
自己推薦であることは受験の準備にも表れており、「志願理由書」という自己PR書を提出しなければなりません。通常の推薦であれば中学校側が「推薦書」という書類を出しますが、その代わりを、自分で用意するのです。
また、特別推薦入試の選考基準は、高校ごとに異なります。野球の強豪校であれば野球の実技を、サッカーの強豪校であればサッカーの実技を、という具合です。
スポーツでなく、文化系の活動であっても同様に、その高校の特色に沿った選考基準があります。
そのほか、高校によっては、出願そのものに条件を設定しています。具体的には、出願できるのは、全国大会やコンクールの入賞経験者に限る、などの条件です。
総じて、特定分野での活躍を入学後も活躍を期待される生徒に向けた入試であるといえます。
私立高校の推薦入試
私立高校の推薦入試は、「単願推薦」と「併願推薦」の二つがあります。公立高校のように、一般推薦・特別推薦といった分類はありません。
なぜなら基本的に、私立高校の入試は学校推薦選抜に一本化されているためです。私立高校の推薦入試は、自己推薦によってではなく学校推薦での受験となります。
単願推薦は「専願推薦」とも呼ばれ、単一の高校のみ推薦入試を受けることを条件とした受験方式。他の高校の推薦入試を受けないことを条件に、合格率が高くなる傾向にあることが特徴です。
ただし、合格後、必ず入学することが前提となります。
併願推薦は複数の高校に対して並行して願書を出せる受験方式。受験する高校を分散させられるため、入学先を確保しやすくなることが特徴です。
高校の推薦入試で行われる試験内容

高校の推薦入試で行われる試験内容は、主に以下のようなものがあります。
個人面接
個人面接は、受験生一人に対して複数人の試験官が面接を行う方式です。
面接の時間は10分程度。内容は、志望動機や中学生活で打ち込んだこと、高校生活でチャレンジしていきたいことなどについてです。
この面接では、受験生の人柄や、初対面の相手からの質問に対してわかりやすく回答できるか、論理的に話を組み立てられるかが見られます。
集団面接、集団討論
集団面接は、一度に複数人の受験生を面接する方式。
試験官が1~3人ほどに対し、3~5名ほどの受験生が一組となって、面接が実施されます。1人当たりの時間配分としては、個人面接と同様に10分程度。
実施の大まかなパターンとして、
- 質問一つに対して、グループの全員が順番に答えていく
- 質問一つに対して、指名された人や挙手した人などが答えていく
という二つがあります。質問内容のパターンは個人面接と大きな差はありませんが、進行の違いに戸惑うこともあるため、準備を怠らないようにしましょう。
集団討論
集団討論は、受験生がグループとなって、課題となるテーマについて話し合う試験です。思考力、コミュニケーション、表現、伝達、説明、協調性などの能力を、話し合いを通して見られます。
話し合いの時間はおよそ30分ほど、グループは5人程度が一般的。話し合いはグループ内の受験生同士で行います。
進行役を試験官が行う場合もありますが、その場合であっても、話し合いには参加しません。
試験官が進行役を行わない場合、受験生に「進行役を決めるかどうか?」という部分から判断をゆだねる場合もあります。
課題となるテーマは、社会問題や環境問題、時事のほか、学校生活や学校行事に関連するものなど、幅が広いです。また、テーマは口頭で発表される場合もあれば、データやグラフなどの記載がある資料と共に伝えられることもあります。
作文・小論文
出題されたテーマについて論じたり、自分の主張を主観的、もしくは論理的・客観的に伝えられるよう記述する試験が、作文・小論文です。
そのパターンは大きく分けて、以下の二つに分類されます。
- 「テーマ」タイプ……テーマに関して自身の意見を書く
- 「資料読み取り」タイプ……グラフや文章といった資料を読み、それに関して自身の意見を書く
また、作文と小論文では書き方の方向性が異なり、別の書き方で答案を書く必要があります。
- 作文……主観的であること(自分がどう思い、どう感じたか)
- 小論文……客観的であること(事実やデータを元に論理的に)
大まかな分類として、上記の違いがあります。
対策の方法も異なってきますから、受験する高校の試験内容を確認しておくことが大切です。
また、塾によってはこうした対策について、専門的な指導を受けられる場合もあります。
高校の推薦入試の合否決定方法

高校の推薦入試の合否判定は、
- 内申点
- 推薦書や志願理由書、自己PR書
- 面接試験の内容
- 実技や適性検査などの結果
といった要素によって決定されます。
仮に全体を100点とした場合、上記の要素がどの程度の配分になっているかは、学校ごとに差があります。
大まかな目安としては、内申点50%、面接25%、作文・小論文25%という比率となっている傾向です。
内申点が非常に大きな割合を占めるため、日々の授業を真面目に受け、定期テストでしっかりと良い点を取っておくことがとても大切です。
高校受験で推薦入試を受けるにはどうする?

基本的に、内申点への対策によって、推薦を受ける基準を満たすことが重要となります。
定期テストで良い成績を残す
学校で実施される定期テストは、内申点に大きな影響を与えます。そのため、定期テストで良い点を取ることは、推薦入試を受けたいのであれば必須級であるといえるでしょう。
また、内申点が一定水準に満たない場合、学校からの推薦をもらえず、推薦入試を受験すること自体が叶わない可能性もあります。
先述した通り、内申点の比率は大きく、50%近くを占める傾向です。そのため、推薦入試を受けることに加え、合格するという観点からも、定期テストの結果は重要です。
定期テスト対策は自分で行うこともできますが、より万全を期し、受験を意識した勉強をするためには、塾での定期テスト対策がおすすめです。
課題や提出物の期限を守る
課題や提出物の期限をきちんと守ることは、推薦入試を対策することにつながります。なぜなら、内申点には、定期テストで良い成績に加えて、課題や提出物の提出も加味されるためです。
そのため、課題や提出物の期限を破ったり、その質が低いと、「定期テストの成績が良かったのに、内申点が悪い」という現象が起こりえます。
これを防ぐためにも、課題や提出物の期限をきちんと守りましょう。
また、大前提として、課題や提出物というのは、「自分のためになるもの」です。宿題は学力を伸ばし、期限通りに提出物を出すことは、今後の人生においても非常に重要なこと。
単なる内申点対策ではなく、学力検査の対策や、今後の人生においてもプラスに働きます。この点も、覚えておきましょう。
日々の授業に真剣に取り組む
日々の授業に真剣に取り組みましょう。なぜなら、授業へ主体的に取り組む姿勢は内申点に影響するためです。
また、授業を真剣に受けることこそ、成績向上の近道でもあります。
定期テスト前に集中的に勉強しても、普段の授業で居眠りしていては、学習効率に限界がありますよね。毎日の授業に真剣に取り組み、ベースがある状態でのテスト対策こそ、十二分な効果が得られます。
また、先生が授業中に口頭で「ここは大事だぞ」、「ここ、テストに出すよ」と話した内容を聞き逃してしまっては、周囲と大きな差がついてしまいます。
そのため、日々の授業に真剣に取り組むことは、いわゆる「コスパの良い」受験対策であるといえます。
部活やスポーツで結果を出す
特別推薦入試、つまり、スポーツ推薦や一芸推薦を受けるためには、その活動で結果を残していることが重視されます。
そのため、もし特別推薦を受けたい場合、その活動に一層真摯に取り組み、結果を残せるよう努力することが対策となります。
また、特定分野での活躍を見るため、高校によって、実施している分野や試験実施の有無が異なります。したがって、志望校が自分の活動の分野で特別推薦入試を実施しているかどうか、確認していくことも大切です。
まとめ
高校の推薦入試とは、内申点や活動実績、面接や作文・小論文などによって、人物を多面的に見て合格を決める入試形式です。
その形式は、公立高校の場合は一般推薦入試と特別推薦入試、私立高校の場合は専願推薦と併願推薦に分かれます。
高校の推薦入試における合否の判定は主に、内申点、推薦書や志願理由書、面接、実技や適性検査などの結果によって決定されます。その内訳は、内申点50%、面接25%、作文・小論文25%程度が、一般的な傾向です。
高校受験で推薦入試を受けるには、定期テストで良い成績を残す、課題や提出物の期限を守る、日々の授業に真剣に取り組む、部活やスポーツで結果を出すなどが挙げられます。
また、推薦入試の実施について、各高校や自治体によって推薦入試の実施や出願の基準、入試の方法は異なります。そのため、自分の志望校や受験先に都度確認し、正しい情報に基づく受験対策を立てていくことが大切です。
そして、面接や集団討論、作文・小論文、定期テストなど、塾で専門的な対策を行うことが可能です。そのため、受験対策において、塾は大きな助けとなります。
ぜひ、塾による内申点対策、推薦入試対策を検討してみてください。


