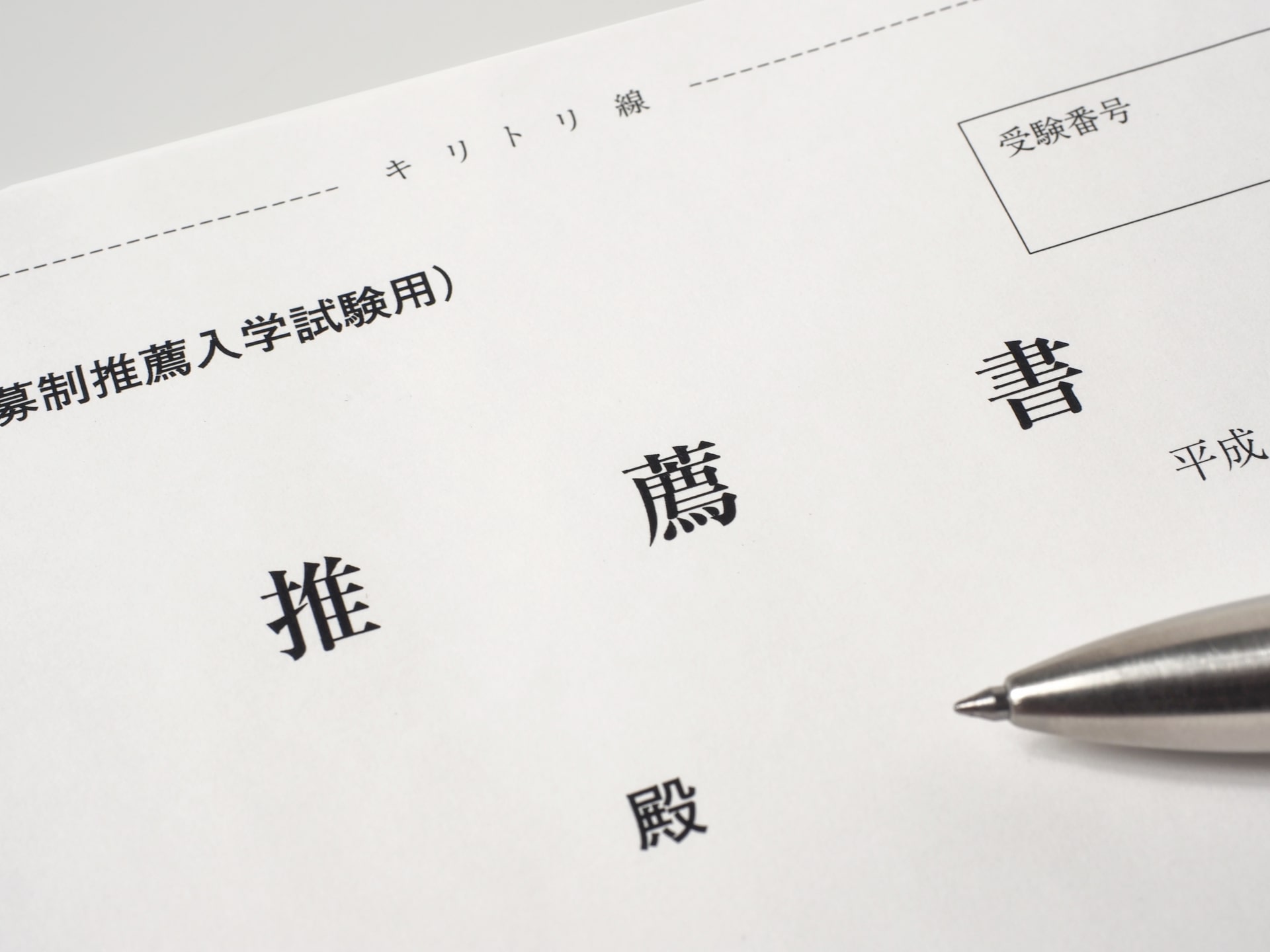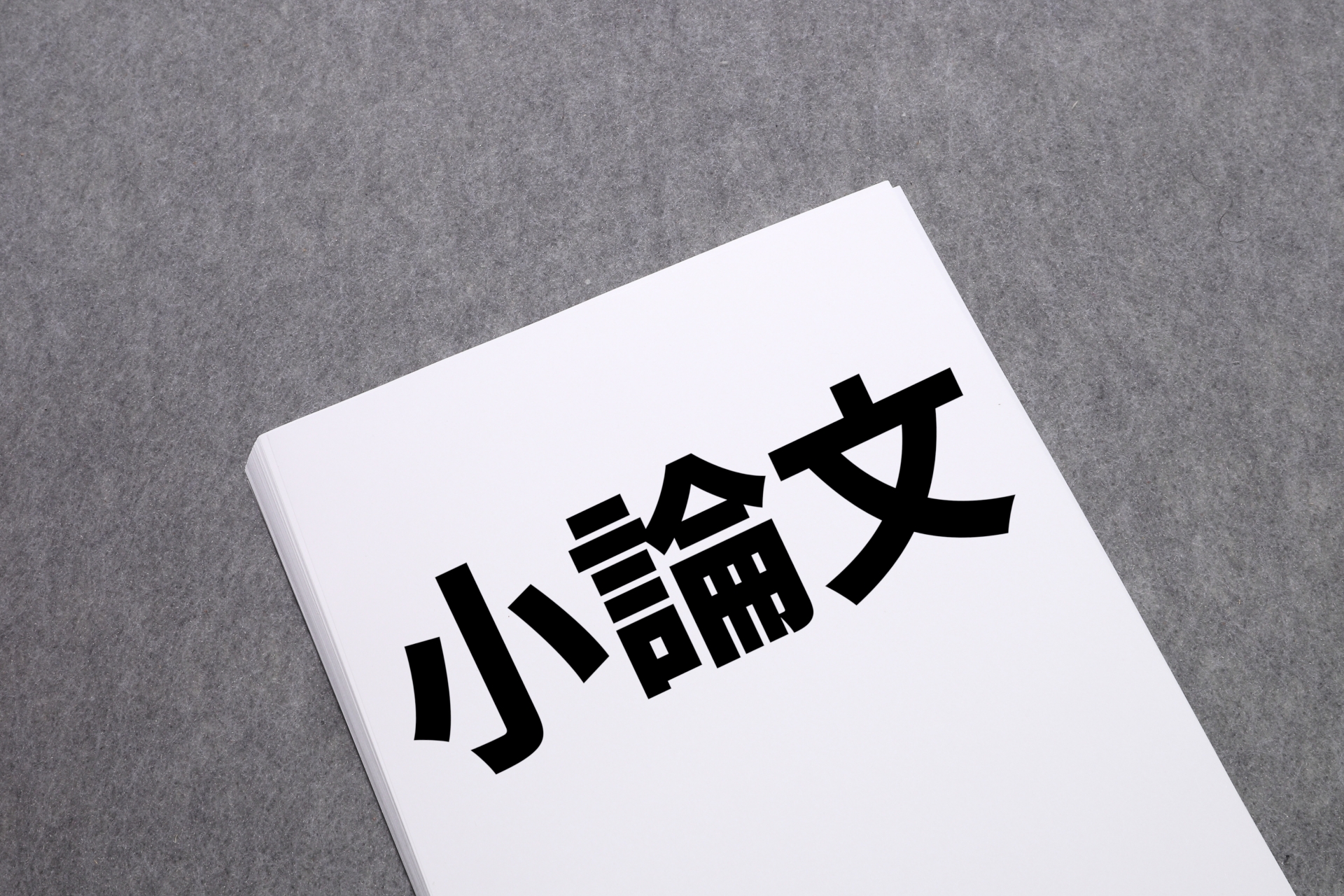初めての高校受験、中学生の皆さんの中には、日程の見通しがわからず、不安になっている方も多いと思います。
「高校受験のスケジュール感ってどんな感じなの?」
「受験勉強はいつから始めればいいの?」
「入試ってどんな仕組みなの?」
など、さまざまな疑問が浮かんできますよね。
多くの中学生の皆さんにとって、高校受験は人生における山場の一つ。その攻略には、長期的な視点と、計画的な準備が求められます。
そしてそのためにはまず、高校受験のスケジュール感をつかむことが大切です。
今回は、高校受験をしようと考えている中学生の皆さんに向けて、各種入試までの日程や、それまでの準備期間について、ご紹介します。
高校受験の準備をいつ頃から始めればいいのかについても触れますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
高校受験はいつごろ行われるの?

実際に入試が始まるのは、3年生の1月頃からです。そしてその時期については、複数の要素によって決定されます。まずは、この点について押さえていきましょう。
公立と私立での違い
公立高校と私立高校の入試スケジュールを比較した場合、入試の日程に数週間から1ヵ月程度の差があります。
そして基本的な傾向として、私立高校の入試日程は、公立高校よりも先行します。
公立高校は地方自治体によって運営されている、県立高校や市立高校などのこと。私立高校とは、一つの企業として運営されている学校のことです。
一定の公的な方針に従うものの、私立高校はその学校の独自色が強くなる傾向にあります。この違いが、日程にも現れている形です。
私立高校の一般入試……1月の下旬
公立高校の一般入試……2月の中旬
ここには、1ヵ月近い間隔があります。「私立高校は、公立高校よりも入試の時期が早い」という点を、覚えておきましょう。
一般入試と推薦入試での違い
日程には、入試形式によっても差があります。推薦入試と一般入試では、推薦入試の方が早い時期に行われる傾向です。
また、受験先が私立・公立のどちらかによっても差があります。
- 私立高校の推薦入試……1月中旬
- 公立高校の推薦入試……2月上旬
私立高校と公立高校の間には、ここでも1ヵ月近くの差があるといえます。
都道府県での違い
公立高校における受験のシステムは、都道府県ごとに決まっています。地域によっては、公立高校の入試日が同一で、一つの高校しか受験できないといったケースが発生します。
また、入試のスケジュールは年度ごとに決まり、その際にシステムの見直しが行われることもあります。入試制度そのものが都道府県によって異なる場合もあるため、情報収集の際は注意しましょう。
受験する年の情報を、しっかり確認しておくことが重要です。
高校受験までの流れ

内申点の確定から合格発表までの、高校受験における一般的な流れについてご紹介します。
11月頃:内申点が確定
通知表の評価である内申点は一般的に、3年生の11月頃に確定します。
三期制の中学校であれば二学期の期末テスト、二期制の中学校であれば後期の中間テストの結果までが、内申点に含まれます。
内申点は、成績表の9教科(英語・数学・国語・理科・社会・音楽・美術・技術家庭・保健体育)によって算出されます。そしてその影響力は現在、学力検査と内申点の比率にして、5:5〜7:3の比率となっています。
7:3の場合で考えると、最大を1000点として、学力テスト(ペーパーテスト)の結果が700点、内申点が300点で計算されるということです。かなりの割合、内申点が含まれることがわかりますね。
この比率や範囲は、厳密にはそれぞれの都道府県ごとによって異なります。中学1年生から3年生まですべての内申点を見る地域もあれば、3年生の成績に限った地域もあります。
12月頃:受験する高校を決める
受験する高校を決めるのは、12月頃。なぜなら、推薦入試の受付について、私立高校であれば1月の中旬から、公立高校の推薦入試であれば1月の末頃から始まるためです。
出願の形式については、郵送の他、インターネットで実施している高校もあります。出願方法も事前に確認しておき、必ず期限までに出願しましょう。
また、この段階で単願と併願を決定しなければならない点にも、注意が必要です。
- 単願(専願)……単一の高校のみを受験し、合格した場合は必ず入学する受験方式。私立高校でよく採用される方式で、他の高校を受験しないことを条件とする分、合格率が高くなる傾向にある。
- 併願……複数の高校に対して、併せて願書を出せる受験方式。第一志望の公立高校、滑り止めの私立高校といった具合に、受験する高校を組み合わせることで、入学先を確保しやすい。
単願は合格率が上がる傾向にありますが、受験のプレッシャーは強くなるでしょう。
併願はリスクを分散できますが、それぞれの高校の受験スケジュールを調整する必要があります。入試日程が被ってしまうと受験できないため、スケジュール調整の重要性は高いといえます。
こうした特徴を踏まえつつ、期限までに出願先と単願・併願を決定しましょう。
1月頃:推薦入試の開始
私立高校における推薦入試・単願入試と、公立高校の推薦入試が1月から始まります。
試験は面接や適性検査、小論文などによって行われ、そこに調査書の内容を加えて合否が決定します。
2月頃:一般入試が開始
私立高校の一般入試が2月初旬から中旬頃、公立高校の一般入試が始まるのは2月下旬頃です。ただし、中には一般入試が3月頃に始まる高校もあります。
私立高校の一般入試は、数学・英語・国語の3教科の筆記試験+面接という形式が一般的。学校によっては、そこに理科・社会を加えた5教科で行われます。
対して公立高校は、国語・数学・英語・理科・社会の5教科の筆記試験+内申点で決定することがポピュラーです。
また2月は、単願入試や推薦入試の合格発表が随時始まっていくタイミングでもあります。
3月頃:合格発表の開始
引き続き公立高校の一般入試が実施されつつ、3月の中旬ごろから順次、合格発表が行われます。
加えて、2月に合格発表された人たちとともに、入学の準備が進んで行くシーズンでもあります。
合格発表については、現地で確認する方法のほか、インターネット上で確認できる学校もあります。また、入試の結果によっては追加合格が発生したり、二次募集がかかる場合もあります。
高校受験の準備はいつから何を始めたらいいの?

最後に、高校受験の準備を始めるタイミングについてもご紹介します。
高校受験の準備は早くから始める
高校入試で出題されるのは、高校3年生で勉強する範囲からだけではありません。中学1年生、中学2年生の勉強範囲からも、多く出題される傾向があります。
こうした基礎的な部分が不安定だと、後からの挽回が難しくなるため注意が必要です。
また、内申点という視点においても早期の対策は有効です。中学1年生の頃からの内申点が考慮される可能性があることを考えると、内申点を取るために、学校のテストを対策しておくに越したことはありません。
そのため、高校受験の準備は早く始めることが得策であるといえます。
中学1年生のとき
中学1年生は、基礎を積み上げる段階です。
勉強は積み上げであり、後から挽回するよりも、あらかじめ下地を作っておいた方が余裕を持てます。追い立てられるように勉強するよりは、ゆったりと進められた方がよいですよね。
また、あらかじめ勉強に取り組んでおくことで、ギリギリになって「予想外に成績が伸びない……」といったアクシデントを予防しやすいでしょう。
加えて、内申点の存在も忘れてはなりません。高校受験における内申点の比率は無視できるものではなく、学校によっては、中学1年生の成績から内申点に加わります。ここを意識するかどうかで、他の受験生に大きな差をつけられるでしょう。
総じて、中学1年生の段階では基礎が重要だといえます。
中学2年生のとき
中学2年生は、積み上げた基礎を固める段階です。
特に塾を利用する場合、2年生の冬から春にかけた1月~3月の間に塾に通い始めれば、勉強時時間は十分確保できます。
中学2年生における1月~3月というのは、受験勉強が本格的に始まる前の準備期間。このうちに苦手科目や苦手な単元を克服しておくことで、中学3年生に進級した後の勉強や受験対策に、スムーズに取りかかれます。
反対に、この時期を逃すと、苦手を残したまま受験対策に突入することとなりかねません。
そのため、中学2年生のうちは、これまでの復習にも注力すべき時期であるといえます。
中学3年生のとき
中学3年生は、本格的な受験対策を行う段階です。
もし、部活などで勉強に使える時間に制限があった場合でも、夏頃から取り組めば、十分な成績向上が望めます。また、人によっては大きな追い上げを見せる場合もあります。
時間を有効に使うためにも、普段の授業はもちろん、中学3年生になるまでの、1年生、2年生の授業も、集中して聞いておきましょう。基本的な授業の内容をきちんと押さえておくだけでも、ずっと楽になります。
志望校を決める秋に焦点を当て、それまでに志望校に合格する学力の土台を作っておくことが重要です。
中学3年生の夏休みまでは基礎固めと苦手の克服、秋からは過去問演習といった形で受験対策を進めていくとよいでしょう。中学1年生、中学2年生の内容を圧縮するような形で勉強した後、受験対策に取りかかることができます。
まとめ
高校受験における試験は中学3年生の1月頃から始まります。具体的な時期については、公立か私立か、一般入試か推薦入試かという点に加え、その学校の都道府県によっても左右されます。
受験までの流れとしては、11月頃に内申点が確定、12月頃に出願します。そして1月頃から続々と、入試が始まります。まずは推薦入試、単願入試が始まり、2月頃からは一般入試が始まります。その後、途中に合格発表が挟まり、3月頃まで一般入試が続きます。
また、受験勉強はできるだけ早く始めることが理想的です。中学1年生のうちから基礎を固めておくことで、精神的な余裕も生まれます。
中学2年生では苦手分野を意識し、できる限り解消しておきます。中学3年生になったら本格的な受験勉強に集中しましょう。特に、秋頃(9〜10月)からは過去問演習を強化し、12月からは受験の直前対策に移ることが一般的です。
今回は、高校受験までの日程や準備期間についてご紹介しました。ここで紹介した内容が、皆さんの受験勉強の計画を立てる際の、参考になれば幸いです。